子どもの考える力を伸ばすーオープン・クエスチョンを意識する
「今日楽しかったことは何?」「どうしてそう思ったの?」
こうした問いかけが、子どもの心をぐっと開き、考える力を育てることをご存じでしょうか。
単に「はい」か「いいえ」で答えられる質問ではなく、子どもの想像力や思考を引き出すのが オープン・クエスチョン です。
幼児期は非認知能力(思いやりや自己肯定感など)をぐんと伸ばせる黄金期です。そこで大人の問いかけが重要な役割を果たします。忙しく子どもとの会話の時間を十分とれない方でも、少し意識するだけで幼児教育、子どもとの関係によい刺激を与えます。本記事では、幼児教育におけるオープン・クエスチョンの力と実践方法をわかりやすく解説します。
オープン・クエスチョンとは?
オープン・クエスチョンとは、子どもが自由に答えられる問いかけのことです。
- 特徴
- 答えが一つに限定されない
- 子どもの考えや感情を自然に引き出す
- 会話のキャッチボールが広がる
例えば、
- 「幼稚園ではどんな楽しいことがあった」→答えが何通りもあり、子どもが考えて発言(オープン・クエスチョン)
- 「幼稚園は楽しかった?」→「はい」か「いいえ」で答える(クローズド・クエスチョン)
子どもがより豊かに語れるのは会話、それがオープン・クエスチョンです。
クローズド・クエスチョンとの違い
クローズド・クエスチョンは「はい/いいえ」で答えられる質問です。
| 質問の種類 | 例 | 特徴 |
|---|---|---|
| オープン・クエスチョン | 「どんな遊びが一番楽しかった?」 | 会話が広がる・思考が深まる |
| クローズド・クエスチョン | 「楽しかった?」 | 短い返答で終わる |
子どもに何か質問されたとき「なぜ」「もし」などオープン・クエスチョンを意識的に使い返答することで、子どもはさらに自分の頭で考えようとします。
オープン・クエスチョンのメリット
オープン・クエスチョンを日常に取り入れると、次のようなメリットを生みます。
- 考える力を育てる
ただ答えるのではなく、自分の意見を整理して伝える練習になる。 - 感情表現が豊かになる
「どうして悲しかったの?」と問うことで、自分の気持ちに気づける。 - 親子の信頼関係が深まる
子どもは「ちゃんと聞いてくれている」と感じ、安心して話せる。 - 想像力を刺激する
「もし空を飛べたら、どこに行きたい?」といった質問で発想が広がる。 - 論理構成力を育てる
具体的な思いや考えを伝えるときは、頭の中をある程度整理してから話す必要があります。
☆参考データ「幼児期から小学4年生の家庭教育調査・縦断調査」(ベネッセ教育総合研究所)https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000715.000000120.html?
※この調査では、幼児期における「学びに向かう力」が小学校入学後の学習態度や思考力にどのように影響するかが明らかにされています。
特に、「学びに向かう力」を構成する5つの力(好奇心・自己主張・協調性・自己抑制・がんばる力)のうち 「がんばる力」 を幼児期に身に付けることが、小学校低学年での「自分から進んで勉強する」という学習態度や、高学年での思考力の向上に結びつくことがわかりました。
さらに、この力を育む要素として、家庭環境における「保護者が子どもの意欲を支えること」や「自分で考えられるように働きかけること」 が重要であるとされています
家庭での対話や働きかけ(=親子の会話や応答)が豊かなほど、子ども自身の学びに向かう意欲や社会性の土台づくりに確かな効果があると読み取れます。
オープン・クエスチョンの具体例
子どもによく言ってしまうセリフを「オープン・クエスチョン」を意識して、言い換えてみましょう。
ポイントは「WHY」「HOW」「IF」を意識して使用することです。
「〇〇しなさい!」→「なぜ○○しなきゃいけないんだと思う?」
「WHY」を意識した会話です。気を付けなければことは否定文として使ってはいけないということです。「なぜできないの」「どうしてやらないのか」などと問い詰めると、子どもは言い訳を考えるようになります。まずは「その気持ちはわかるけど・・・それでも」と、共感から入りましょう。
「どうしてこんなこともわからないの!」→「どうしたらわかるようになるだろう?」
「HOW」を意識した会話です。「どうしたらできるようになるだろうね」と、こちらもまずは寄り添うことから始めましょう。一つの正解を求めず、まずは子どもの考えを受け止め、いろんな考えを引き出すことが重要です。
「なんでできないの?」→「もし〇〇だったら、~できるかな?」
「IF」を意識しています。思わず使ってしまう「なんでできないの」は子どもの挑戦する気持ちを奪ってしまいます。例えば「もしお母さんがここまで手伝ったら、できるようになるかな」などと「IF」を使い、提案してみることで子どもは自分で気づいたり、新しい方法を思いつくこともあります。
子どもを否定する言い方ではなく、意欲をわかせる会話を意識してみましょう。
(参考資料『子育てベスト100』加藤紀子)
☆絵本の読み聞かせの中にも「豊かな会話」を取り入れることは有効です。
(絵本の読み聞かせと会話はこちらの記事を参考にしてください。)
https://lycopo.com/『しろいうさぎとくろいうさぎ』から考える絵本/
https://lycopo.com/『スイミー』と幼児教育-〜読み聞かせと会話で育/
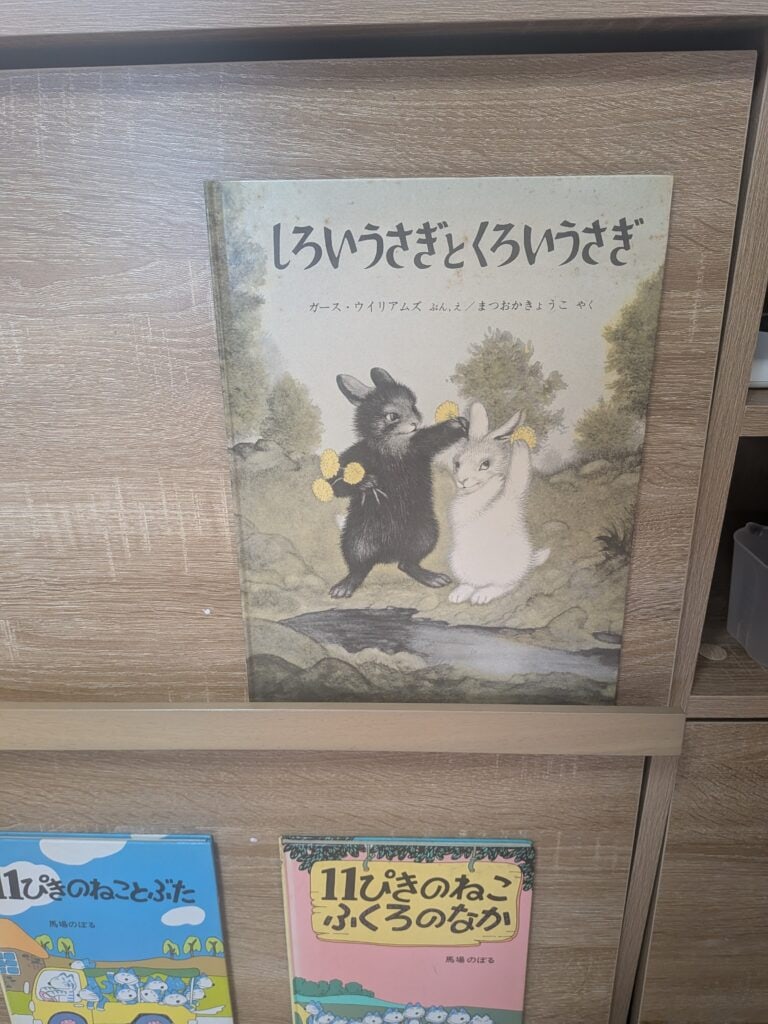
Q&A(まとめ)
Q1. 子どもが「わからない」と答えて会話が止まってしまうときは?
A1. そんなときは「じゃあ、もしこうだったらどう思う?」と別の視点を提示するとよいです。想像の幅を広げることで、子どもが安心して考えを話しやすくなります。
Q2. 兄弟や友達とケンカしたとき、どんな質問が効果的ですか?
A2. 「どうしてイヤだと思ったの?」や「相手はどんな気持ちだったかな?」と問いかけることで、自分の気持ちと相手の気持ちを整理できます。これは“共感力(相手の心を理解する力)”を育てる大切な一歩です。
Q3. 忙しくて長い会話ができないときも、オープン・クエスチョンは使えますか?
A3. もちろんです。「今日一番うれしかったことは?」と短い問いかけでも十分効果があります。短いやりとりを積み重ねることで、子どもは「聞いてもらえている」という安心感を得られます。
☆ご希望の方はオンライン15分何でも相談(無料)をご利用ください。
〇 無理な勧誘なし 〇 パパ・ママどちらの参加も歓迎 〇カメラOFFでもOK 〇LINE通話で実施
※お申込みは公式ライン、もしくはお問い合わせフォームから「無料面談希望」と記入してご連絡ください。
☆体験ベビーシッター(2,000円/1時間 ※特別価格(税込)最大4時間)も募集しています。
体験後にすぐご入会いただく必要はありません。
幼児教育は「今しかできない」貴重な教育です。
今しかできない「幼児教育」──リコポ幼児教育が選ばれる理由
ご家庭に合った最適なサポート方法を、ゆっくり一緒に考えていきましょう。
執筆:中山 快(株式会社リコポ 代表)