読書のマタイ効果とは?学力格差と幼児期からできる対策
「マタイ効果」という言葉をご存じでしょうか。これは社会学者ロバート・K・マートンが提唱した有名な概念です。「富める者はますます富み、貧しい者はますます貧しくなる」という新約聖書『マタイによる福音書』ある言葉が語源となっています。マートンは特に 学問・科学の世界 において、この現象を指摘していますが、今やこの言葉は経済、生活、インスタやYou tubeの登録者数に至るまでいろいろなところに当てはめることができます。
先日、名刺のデザインを依頼しようとフリーランスの人が登録するサイト(ココナラやクラウドワークス、ランサーズのようなサイト)にアクセスしたのですか、一部のトップの口コミ数と、その他の層との差が歴然としていました。トップに掲載されるような人は何百の口コミ数を持ち、一方で全く星のついていない口コミ数「0」の人が多数います。そのような状況で、私はどうしたかというとやはり「0」の人には依頼せず、口コミ数は30くらい、評価は「4,5」でしぼり、次に実際にクリックしてみて、自分の思い描くデザインに合っているか確認して依頼をしました。
名刺や広告のデザインをしてくれる人は無数にいます。検索のページ数は数十にもいたり、とても全部調べることはできません。まずは口コミ数や評価でふるいにかけ→実際のデザインを見て決める。これは飲食店でも、地元の歯医者さんですらそのように決めることはもはや珍しくないと思います。結果として口コミ数が多い人やお店は増々お客が来て儲かり、そうでない人やお店はいくら腕がよくても客はなかなか来ず、貧しくなってゆく・・・何となくわかる構造だと思います。
そして、この「マタイ効果」は教育面でも顔を出してきます。しかもかなり色濃く。場合によっては残念ながら。今日はこの教育における「マタイ効果」について触れていきます。
☆ じつはこのマタイ効果で有名な学者は2人います。今触れたこの「社会学者」であるマートンと、もう一人は認知心理学・教育心理学 の分野にて「マタイ効果」を応用したキース・スタノヴィッチです。最初に「マタイ効果」を提唱したのはマートンですが、本日はスタノヴィッチによる「教育におけるマタイ効果」について主にお伝えします。
マタイとは誰か
マタイは新約聖書に登場する人物でイエス・キリストの12人の弟子(使徒)のひとりです。ユダヤ人で元は税金徴収人していました。先日ユダヤ人についての記事を書きましたが、その時彼らはローマの求めに応じず、ユダヤ教からキリスト教に改宗しなかったために、迫害を受けたという話を少しだけしました。税金取立人はローマに雇われ、税金を徴収し、その一部を収入にする職業です。彼は同胞のユダヤ人からひどく嫌われました。そして、その後イエスから「わたしに従いなさい」と声をかけられ、仕事を捨てて弟子になったと伝えられています。
その後新約聖書の最初の書物「マタイによる福音書」を書いたとされ、イエスの行いや言葉をまとめる同時に、ユダヤ人への説得を試みていたとされます。
そして、この新約聖書『マタイによる福音書』25章29節「富める者はますます富み、貧しい者はますます貧しくなる」の言葉が「マタイ効果」へとつながります。
科学・学問におけるマタイ効果
- 有名な研究者や権威ある学者が発表すると、その成果は注目されやすい。
- 同じ内容でも無名の研究者が出した場合、評価されにくい。
- つまり「名声や信用がある者は、さらに名声を集めやすい」という構造。
日本でもノーベル賞も受賞した山中伸弥元教授が研究の発表をすれば、日本中が注目します。一方で、無名の研究者は何か権威のある賞を受賞したり、実際にその研究が技術として確立されるか、商品化されるまでなかなか注目されません。これは決して日本だけではなく、世界共通のものです。これが マタイ効果「実力だけでなく、すでに持っている名声が影響する」 という現象です。
読書のマタイ効果
心理学者 キース・スタノヴィッチが提唱した 読書・読解力の発達 にマタイ効果を当てはめたもので、「本を読む子はさらに本を読む力がつき、読まない子はますます差が開く」という現象を指します。
仕組みをまとめます。
〇 読める子の好循環
- 読解力がある → 読書を楽しめる
- 楽しいから読む量が増える
- 語彙・知識・背景理解が広がる
- 学校の教科全般で理解が進む
- 成績や自信が向上 → さらに読書意欲が高まる
→ ポジティブスパイラル に入る
〇 苦手な子の悪循環
- 読解に時間がかかる → 本がつらい
- 読書量が少ない → 語彙や知識が不足
- 授業が難しくなる
- 自信を失い、さらに読書を避ける
- ますます差が拡大
→ ネガティブスパイラル に入る
何となく想像できると思います。幼少の土台を築くところがその後の技術面、メンタル面にも影響してきます。
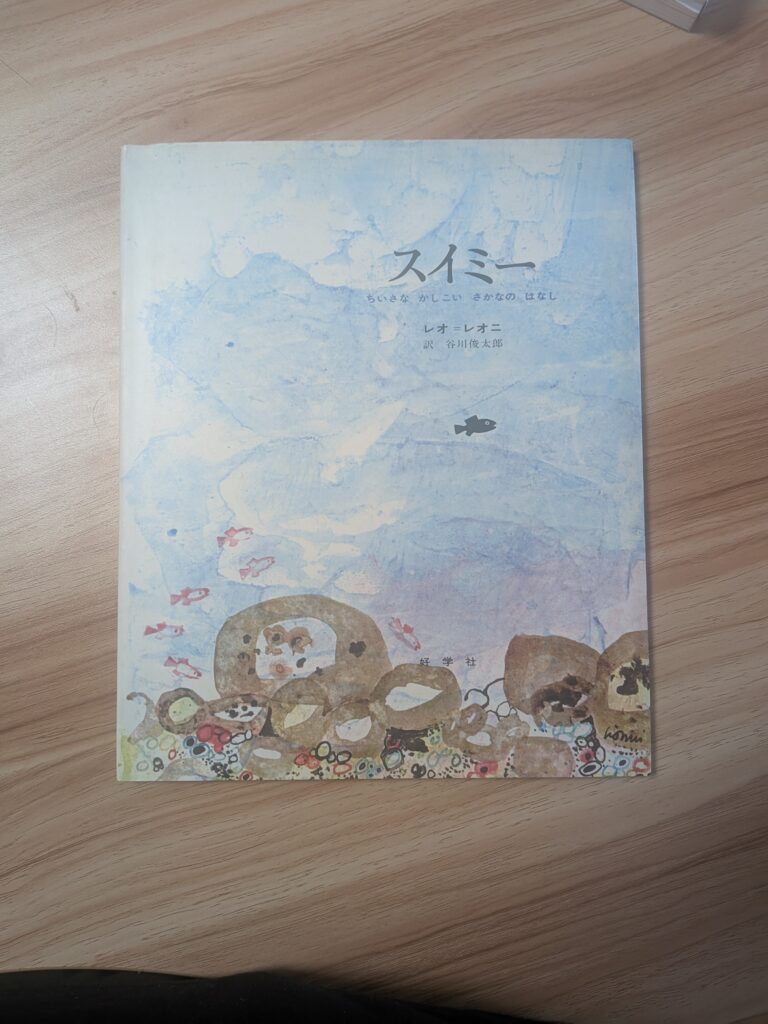
影響する要素
- 語彙力
本を読む子は、日常会話では出てこない高度な語彙を自然に習得していく。 - 背景知識
読書で多様な世界観や事実を知り、理解力の土台が厚くなる。 - 集中力・持続力
本を読み切る経験が、認知的スタミナを養う。 - 自己肯定感
「本が読める」「理解できる」という体験が自信につながり、さらに学習意欲を促す。
私は受験生の国語を教えていた時期もありましたが、本当にこれは習慣があるかないかで如実に表れます。習慣がない子は文章に入り込むことができず、開始の合図があってもぼーしたり、きょろきょろしたりと問題に取り掛かれません。文章に慣れさせることがとても大変でした。
(こちらの紀伊国屋のサイトが読書と学力について詳しくまとめてくれています。参考にしてください。https://mirai.kinokuniya.co.jp/2021/09/27322/?)
読書によるマタイ効果を防ぐためには
(1)早期介入
- 幼児期からの読み聞かせ・音読習慣をつくる
- 「文字を読むこと」より「ことばを楽しむこと」に重点をおく
(2)アクセス機会の確保
- 家に本が少ない子にも学校や地域図書館を利用する(正直に言って、私の経験でも家の棚にたくさんの本のある家庭の子は、比較的勉強熱心で、いい大学に進んでいました。)
- 電子書籍・アプリはしっかりと大人が関わったうえで(使用アプリの厳選、一緒に利用するなど)アクセスする
(3)達成体験の積み重ね
- 難しすぎない本から始める
- 読み切れた達成感を与え、「自分は読める」という感覚を育む←とても大事です
(4)保護者の関わり
- 読み聞かせや一緒に本を読む時間を持つ
- 親自身が読書している姿を見せる「モデリング効果」←かなり有効です。基本的に子どもは親を見て成長します。
Q&A(まとめ)
Q1. 読書のマタイ効果とは何ですか?
A. 読める子どもは本を楽しみさらに力を伸ばし、読みにくい子は読書を避けて差が拡大する現象を指します。心理学者キース・スタノヴィッチが提唱しました。
Q2. どんな力に影響しますか?
A. 語彙力や背景知識、理解力、集中力、さらには自己肯定感まで広く影響します。読書量の差が積み重なり、学力格差へ直結します。
Q3. 子どもの読書格差を小さくするには?
A. 幼児期からの読み聞かせや音読習慣、図書へのアクセス確保、子どもに合った本を選んで達成体験を積ませることが有効です。
読書のマタイ効果は「読める子はますます読む力をつけ、苦手な子はさらに読書から遠ざかる」
という 教育格差拡大のメカニズム を示しています。
だからこそ、言語をどんどん吸収していく幼児期の教育や、本を読み切る成功体験がとても重要になっていきます。
絵本の読み聞かせや、有効な会話法などに触れた記事です。参考にしてみてください。https://lycopo.com/『しろいうさぎとくろいうさぎ』から考える絵本/
https://lycopo.com/『スイミー』と幼児教育-〜読み聞かせと会話で育/
☆ご希望の方はオンライン15分何でも相談(無料)をご利用ください。
〇 無理な勧誘なし 〇 パパ・ママどちらの参加も歓迎 〇カメラOFFでもOK 〇LINE通話で実施
※お申込みは公式ライン、もしくはお問い合わせフォームから「無料面談希望」と記入してご連絡ください。
☆体験ベビーシッター(2,000円/1時間 ※特別価格(税込)最大4時間)も募集しています。
体験後にすぐご入会いただく必要はありません。
幼児教育は「今しかできない」貴重な教育です。
今しかできない「幼児教育」──リコポ幼児教育が選ばれる理由
ご家庭に合った最適なサポート方法を、ゆっくり一緒に考えていきましょう。
執筆:中山 快(株式会社リコポ 代表)