「共同注意」で育つ! 幼児教育に欠かせない親子のまなざし共有
「ブーブー」「ウーウー」と言って子どもが指を指す。そしてその指した先を一緒に見て「ほんとだね。猫さんがいるね」と笑う。これがもうとても重要な教育になっています。 その瞬間こそが、教育や発達のカギとなる「共同注意」です。
共同注意とは、親と子が同じ対象を見て、その体験を共有することです。シンプルに思えるやりとりですが、実は言葉の発達や思いやりの芽生えなど、子どもの成長に大きな影響を与えます。本記事では、共同注意とは何か、共同注意を親が「意識」して行うことでどんな力を育むのか、そして日常や絵本読み聞かせの時にどう実践できるかを、幼児教育の視点からわかりやすく解説します。
共同注意とは
「共同注意」とは、大人と子どもが同じ対象に意識を向け、それを共有することです。
- 例:親が「ワンワンだね」と犬を指さす → 子どもも犬を見る → 互いに笑顔を交わす。
このように「同じものを一緒に見ている」という共有体験は、発達心理学で非常に重要とされています。
指差し行動は、共同注意の典型的なサインです。生後9〜12か月頃から芽生え、2歳ごろにはかなり豊かに発達していきます。
共同注意によって得られる能力
共同注意を通して育まれる力は多岐にわたります。
- 言語の発達
- 親が対象を指差しながら名前を教えることで、語彙がぐんぐん増える。
- 「音」と「意味」を結びつける最適な場面になる。
- 社会性・思いやり
- 他者と「同じ体験をしている」という感覚が、共感性を育む。
- 将来の協力や友だち関係の基盤になる。
- 認知の発達
- 大人が少し先のことを示すことで、子どもの「最近接領域(ZPD)」に働きかけられる。
- 「ひとりではできないことを、誰かと一緒ならできる」体験が積み重なる。
乳幼児期は言語能力が爆発的に伸びる時期であり、言語の基盤がつくられる時期です。この時期にしっかり言葉を投げかけることは、今後にも大きく影響していきます。
☆言語発達の流れのかんたんなまとめ
- 乳児期(0〜1歳半)
- クーイング(あー、うー)
- 喃語 なんご(ばばば、ままま)
- 1歳前後から「ママ」「ブーブー」といった初語が出始める。
- 幼児前期(1歳半〜3歳頃)
- 語彙が急増(「語彙の爆発期」とも呼ばれる)。
- 2語文「ママ きた」「ワンワン いた」などを話し始める。
- 幼児後期(3〜6歳頃)
- 文法が整ってくる。
- 「なぜ?どうして?」と質問が増え、思考力と言語が連動し始める。
- 会話を通じて社会性や感情表現も大きく伸びる。
共同注意の具体的方法
家庭で簡単に取り入れられる方法をご紹介します。
- 指差しを活用する
「見てごらん!飛行機!」と親が示す。子どもも空を見上げる。 - 名前や特徴を言葉にする
「赤い車だね」「大きな音がするね」など、具体的な語彙と体験を結びつける。 - 子どもの視線を追う
子どもがじっと見ているものに気づき、「〇〇に興味があるんだね」と言葉を添える。 - リズムを大切に
大人が先に見せるだけでなく、子どもが示したことに大人が合わせることも大事。
共同注意において親の関わり方
共同注意は一方的な「教え込み」では成り立ちません。
ポイント
- 受け止める姿勢
子どもが示したことに「ほんとだね!」と反応する。 - 余裕をもつ
忙しい時でも「一瞬だけでも一緒に見る」ことを心がける。 - 感情を共有する
ただ見るだけでなく「きれいだね」「楽しいね」と気持ちを伝える。
逆に、子どもの反応に対してそっけない態度をとる、例えばスマホを見ながら「ふーん」で終わらせるたり、子どもの視線を無視したりすることは「自分の気づきは大切にされていない」と感じてしまい、外部のものに関しての興味を失わせてしまいます。
共同注意と幼児教育
幼児教育において、共同注意は基礎中の基礎で、保育士の先生方も意識して行ってくれています。
- 園生活での共同注意
先生が「今日はお花が咲いているね」と指差す → 子どもたちが一緒に観察する。 - 学びの入り口
集団生活でも「同じものに注意を向ける」ことが学習のスタートになる。
さらに、共同注意が豊かな子どもは、授業や遊びにおいて集中力や理解力が伸びやすいという研究結果もあります。
(共同注意についての詳しい研究です。「乳幼児の発達における共同注意関連行動について」)※ぱっと見難しそうですが、結構分かりやすくまとめてくれています。
共同注意と絵本での活かし方
絵本の読み聞かせは、共同注意を自然に育む最高の時間です。
活用のコツ
- 指でなぞる
絵のキャラクターを指差しながら読むと、子どもも同じ場所を見やすい。 - 質問する
「どっちが大きいかな?」「誰が泣いているかな?」と問いかける。 - 感情を共有する
「わぁ、怖そうだね」「かわいいね」と、子どもの反応に共感する。 - 繰り返し読む
繰り返すことで、言葉とイメージの結びつきがより強固になる。
(絵本の読み聞かせについてはこちらに詳しく書いています。参考にしてみてください。『しろいうさぎとくろいうさぎ』から考える絵本教育とシッター活用)
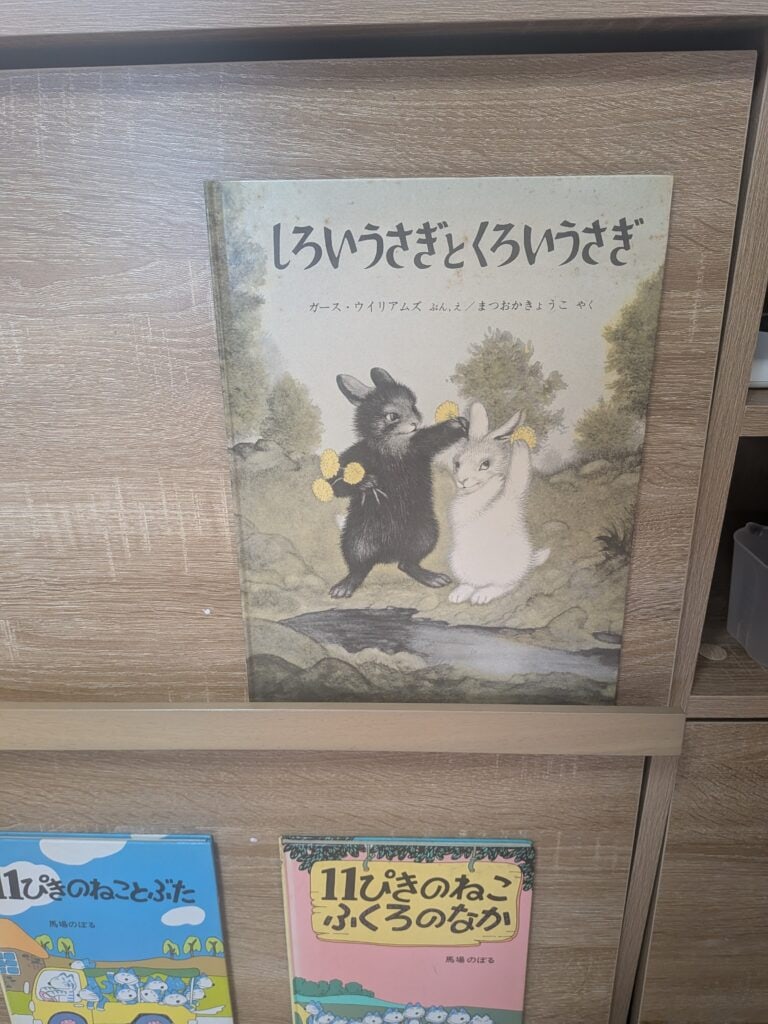
Q&A(まとめ)
Q1:共同注意って、なぜそんなに大事なの?
A: 言葉の発達・社会性・認知力の基盤になるからです。親子で同じものを見て「共有する」体験が、語彙力の伸びや思いやりの芽生えに直結します。特別な教材よりも、日常の「見てごらん!」が最大の教育になります。
Q2:忙しい時に子どもが指差してきたら、どう対応すればいい?
A: 一瞬でも構いません。「ほんとだね」と目線を合わせて共感することが大切です。数秒のやりとりでも、子どもにとっては「自分の気づきを大事にしてもらえた」という大きな安心感と学びにつながります。
Q3:絵本の読み聞かせで、共同注意を活かすには?
A: 指で絵をなぞる・質問をする・感情を共有することがポイントです。「誰が笑ってるかな?」「こわいね」などと語りかけることで、子どもは自然に共同注意を体験し、言葉と感情の理解を広げていきます。
☆ご希望の方はオンライン15分何でも相談(無料)をご利用ください。
〇 無理な勧誘なし 〇 パパ・ママどちらの参加も歓迎 〇カメラOFFでもOK 〇LINE通話で実施
※お申込みは公式ライン、もしくはお問い合わせフォームから「無料面談希望」と記入してご連絡ください。
☆体験ベビーシッター(2,000円/1時間 ※特別価格(税込)最大4時間)も募集しています。
体験後にすぐご入会いただく必要はありません。
幼児教育は「今しかできない」貴重な教育です。
今しかできない「幼児教育」──リコポ幼児教育が選ばれる理由
ご家庭に合った最適なサポート方法を、ゆっくり一緒に考えていきましょう。
執筆:中山 快(株式会社リコポ 代表)