サリー・アン課題でわかる「他人の心を読む力」子どもの“心の理論”
3歳児に、こう尋ねてみたらどう答えるでしょうか?
「サリーとアンがいます。サリーはおはじきをカゴに入れて外に出かけました。
その間に、アンがそのおはじきをカゴから箱に移しました。
さて、サリーが帰ってきたとき、おはじきはどこにあると思うでしょう?」
この問いが「サリー・アン課題」と呼ばれる、有名な発達心理学のテストです。
子どもがどのように答えるかによって、「他人の心を想像する力」――つまり“心の理論”の発達段階が見えてきます。
本記事では、この課題の意味と、そこから見える幼児の発達、そして親や教育者ができる支援のあり方について詳しく解説します。
サリー・アン課題とは?─他人の「信念」を想像できるか
サリー・アン課題は、1985年に心理学者バロン=コーエンらによって開発された、「心の理論」を調べる代表的な実験です。
サリーとアンという2人の登場人物を使い、子どもが「他者の誤った信念」を理解できるかどうかをテストします。
実験の流れ
- サリーが“おはじき”をカゴに入れます。
- サリーが部屋を出ます。
- その間にアンが、おはじきを箱に移します。
- サリーが戻ってきます。
- 質問:「サリーはおはじきをどこにあると思っているでしょう?」
子どもたちの一般的な回答と発達の違い
この質問に対し、4歳未満の多くの子どもはこう答えます。
「箱の中!」
彼らは「現実(おはじきが箱にある)」をもとに判断します。
つまり、サリーが何を知らないかということをまだ想像できないのです。
一方、4歳頃を過ぎた子どもはこう答えるようになります。
「カゴの中!」
サリーはおはじきが移されたことを知らない、という「他人の立場に立った推測」ができるようになります。
この変化こそが、「心の理論」が発達し始めた証拠なのです。
サリーとアン課題 (Wikipedia) 分かりやすくまとめられています
サリー・アン課題からわかること──“他人の心を読む”ということ
この課題が示すのは、人間の社会的認知能力の発達段階です。
子どもは成長とともに「他人の考え・感情・意図」を理解し始めます。
それが“心の理論”です。
心の理論とは?
- 他人が自分と異なる信念・感情・意図をもつことを理解する力
- 「他者視点」を持ち、相手の行動を予測したり共感したりする基盤
この力は、コミュニケーション・協調・道徳意識・共感性など、社会性の中核を支えています。
※非認知能力・共感力についてはこちらを参考にしてください。
「非認知能力]とは。改めて非認知能力をまとめます
「共感性」を養う幼児教育 「思いやりのある子ども」は幸福度が高い
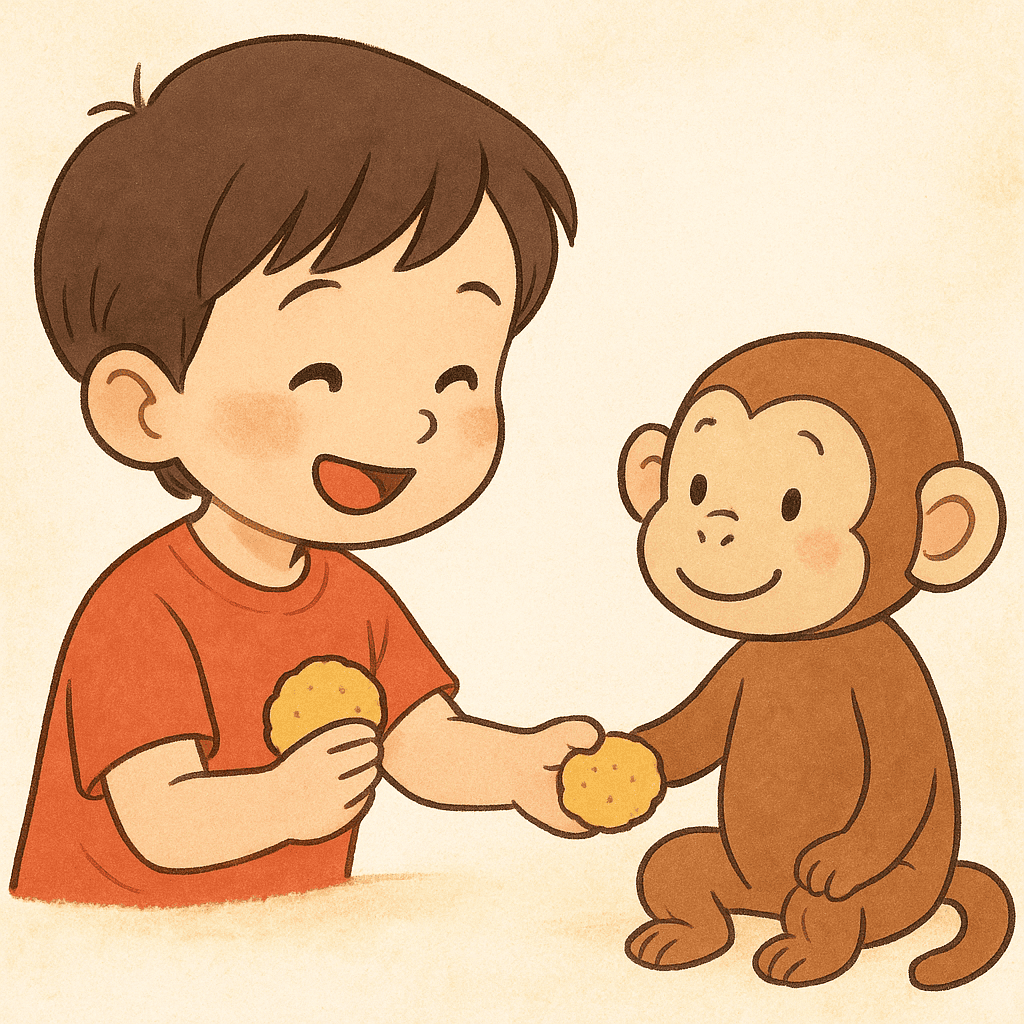
一次の心の理論とサリー・アン課題の関係
サリー・アン課題が測定するのは、「一次の心の理論」です。
これは、「Aさんはこう思っている」という単一の他者の信念を理解する力のこと。
- 一次の心の理論:
→「サリーはおはじきがカゴにあると思っている」と想像できる力。 - 二次の心の理論:
→「アンは、サリーが“カゴだと思っている”と知っている」と、
他者が他者をどう理解しているかを考えられる力。
子どもはまず一次の心の理論を獲得し、それが土台となって、より複雑な人間関係の理解(嘘・秘密・皮肉など)が可能になります。
心の理論と幼児教育──「思いやり」の芽を育てる
サリー・アン課題で見られるような「他者理解の芽」は、幼児教育の中で大切に育てることができます。
1. ごっこ遊びや物語の力
ごっこ遊びや絵本の読み聞かせは、子どもが他人の視点を模倣する貴重な機会です。
「もし自分が○○だったらどうする?」という想像が、心の理論の発達を促します。
2. 対話の中での“心の言葉”
大人が「○○ちゃんは悲しかったのかな」「サリーはどう思っただろうね」と、
感情語や心理語を使う会話を重ねることで、子どもは「他人にも心がある」と学びます。
3. 失敗やけんかの場面も教材に
トラブルの際に「相手の立場から考える」練習をすることで、
ただのしつけではなく、心の教育が行えます。
「嘘をつけるようになる」ことの意義──悪ではなく成長の証
「心の理論」を十分獲得すると、子どもは嘘をつけるようになります。
「嘘をつける」ようになるのも、心の理論の発達と深く関係しています。
他人の信念を操作できるということは、「相手の心を理解している」証拠でもあるのです。
もちろん、道徳的な指導は必要ですが、発達心理学的には「他人の視点を持てる段階」に到達したサインです。
親としては、嘘を頭ごなしに叱るよりも、
「どうしてそう言いたくなったの?」
と、気持ちの背景を聞くことで、より健全な心の成長を促せます。
※嘘はあるいことばかりではありません。こちらの記事をご覧ください。
子どもの「嘘」や「汚い言葉」成長のサインと親の向き合い方
親の心の持ちよう──「心を理解する心」を育む環境を
サリー・アン課題が教えてくれるのは、
子どもが“他人の心を理解する力”を持つには、まず大人がそれを見せる必要があるということです。
親が
- 「相手の気持ちを考える姿勢」
- 「感情を言葉で表す習慣」
を日常で示すことで、子どもは自然とその姿を模倣します。
子どもの“心の発達”は、親の心の姿勢から始まるのです。
まとめ:心を読む力は、思いやりの第一歩
| 発達段階 | サリー・アン課題での答え | 発達的意味 |
|---|---|---|
| 3歳頃まで | 「箱の中!」(現実のみ) | 他者の視点がまだ理解できない |
| 4〜5歳頃 | 「カゴの中!」(誤信念理解) | 一次の心の理論を獲得 |
| 6歳以降 | 嘘・皮肉・秘密の理解 | 二次の心の理論へ発展 |
“心を読む力”は、単なる知能ではなく「人と共に生きる力」です。
リコポ幼児教育では、このような「思いやり」や「他者理解」の芽を、日々の遊びと対話の中で丁寧に育んでいます。
Q&A(まとめ)
Q1. サリー・アン課題は家庭でもできますか?
A はい、家庭でも簡単にできます。
ぬいぐるみやおもちゃを使って、「サリー(A)」と「アン(B)」を演じてみましょう。
「サリーがカゴにお菓子を入れて出かけたあと、アンが箱に移しました。サリーはどこを探す?」と質問するだけです。
3歳頃までは現実通りの答え(箱)を選びますが、4歳前後になるとサリーの立場を考え、「カゴ」と答えるようになります。
お子さんの“心の成長”を楽しく確かめられる遊びです。
Q2. サリー・アン課題に正しく答えられないと発達が遅れているのですか?
いいえ、そうとは限りません。
心の理論の発達には個人差があります。
早くから他人の気持ちを察する子もいれば、少し時間をかけて身につける子もいます。
家庭で「○○ちゃんはどう思ったかな?」「悲しかったかな?」と感情語を使う会話を増やすことで、他者理解の力は自然と育ちます。焦らず、対話を通して心を育てていくことが大切です。
Q3. 嘘をつくようになったとき、どう受け止めるべきですか?
「嘘=悪いこと」と決めつけずに、その背景を見てあげましょう。
嘘をつくには「相手が知らないことを理解する力」が必要で、これは心の理論の発達を示すサインです。
大人は「どうしてそう言ったの?」と優しく聞き、子どもの気持ちや不安を言葉にさせてあげることが大切です。
嘘を叱るよりも、心を理解する練習のチャンスとして捉えましょう。
☆ご希望の方はオンライン15分何でも相談(無料)をご利用ください。
〇 無理な勧誘なし 〇 パパ・ママどちらの参加も歓迎 〇カメラOFFでもOK 〇LINE通話で実施
※お申込みは公式ライン、もしくはお問い合わせフォームから「無料面談希望」と記入してご連絡ください。
☆体験ベビーシッター(2,000円/1時間 ※特別価格(税込)最大4時間)も募集しています。
体験後にすぐご入会いただく必要はありません。
幼児教育は「今しかできない」貴重な教育です。
今しかできない「幼児教育」──リコポ幼児教育が選ばれる理由
ご家庭に合った最適なサポート方法を、ゆっくり一緒に考えていきましょう。
執筆:中山 快(株式会社リコポ 代表)