子どもの“ひとりごと”は成長の宝?〜乳幼児期の呟きについて
「うちの子、ひとりでずっとしゃべってるんです……」
「誰と話してるの?と思うくらい、おもちゃに語りかけていて。」
乳幼児を育てるご家庭では、こんな光景をよく目にしますよね。
一見“意味のないおしゃべり”のようですが、実はこの 「ひとりごと」こそが、子どもの思考と社会性を育てる大切なプロセス なんです。
心理学者ピアジェとヴィゴツキーも、この“ひとりごと”をめぐって熱い議論を交わしました。
今日は、教育心理の観点から「子どものひとりごと」をやさしく解説します。
子どもがひとりごとを言うのはなぜ?
● よくある場面
- おもちゃを積みながら「こっちかな?」「あ、崩れちゃった!」
- 絵本をめくりながら「これネコさんだね」
- 一人遊び中に「お母さん、いまね〜」と空想の相手に話しかける
こうした行動は、自分の中の考えを整理するための“声に出す思考” です。
言葉を使って「次はこうしよう」「これは違う」と確認しながら、思考を組み立てているのです。
ひとりごと=社会性の始まり
一見「孤立してる」ように見えて、実はその逆。
ひとりごとは、社会性の芽が出はじめた証拠 です。
なぜなら――
- 言葉はもともと「他者との関わり」から育つ
- その関わりを“自分の中で再現”しているのがひとりごと
つまり、社会的な対話が内側で続いている状態 なんです。
子どもは、ママやパパとの会話をまねて、ひとりでも対話を繰り返しています。
「自分との会話」ができる=他者との会話ができる基礎になる。これが“社会性の土台”です。
子どもの「ひとり言」止めなくて大丈夫「嘘」は成長の証拠(2024年/講談社コクリコ)
ひとり言を「止めなくて良い」「成長の証」と捉える視点がわかりやすく書かれています。
ピアジェの考え:「ひとりごとは未熟な言葉」
スイスの心理学者 ジャン・ピアジェ は、子どもの“ひとりごと”を「自我中心的言語(egocentric speech)」と呼びました。
ピアジェの見方では――
- 子どもは他人の立場をまだ理解できず
- 自分の世界でしか考えられない
- だから“自分にだけ通じる言葉”を使う
とされました。
つまり、「社会的に未熟な段階の言語」 とみなされていたのです。
ピアジェにとって、ひとりごとは成長とともに“消える”もの。
他者との会話が増えるほど、自然と減っていくと考えられていました。
※ピアジェの発達教育についての記事です。ピアジェは教育学についてとても重要な人物です。
子どもは“小さな科学者” ピアジェの発達段階理論と幼児教育の関係
それに異を唱えたヴィゴツキー
ソビエトの心理学者 レフ・ヴィゴツキー は、ピアジェとは真逆の立場をとります。
「ひとりごとは、成長の途中で生まれる“考えるための言葉”である。」
ヴィゴツキーは、言葉が次のように発達すると考えました。
- 社会的言語(他者との会話)
↓ - ひとりごと(プライベートスピーチ)
↓ - 内言(声にならない思考)
この流れを 「言語の内化」 と呼びます。
つまり、他人との会話が内面に取り込まれ、自分自身への“内なる対話”に変化していくということです。
※ヴィゴツキーもまた現代教育学の始祖であり、権威でもあります。ヴィゴツキーの最近接領域の考え
は幼児教育において重要なキーワードです。その最近接領域の記事です。
【個別教育の力】「最近接領域」に働きかけるベビーシッターの強み
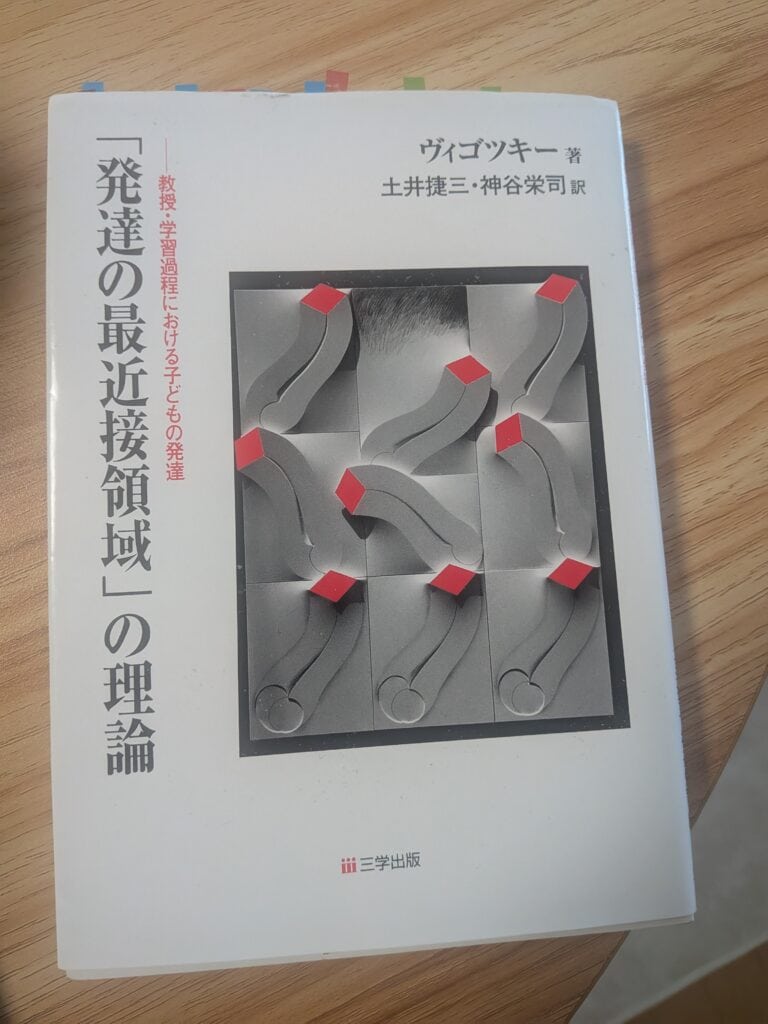
実験が示す「ひとりごとの力」
ヴィゴツキーの弟子たちは、子どもが難しい課題に取り組むときの様子を観察しました。
すると――
- 難しい場面になるほど、子どもはひとりごとを増やす
- 問題を解けるようになると、声を出さずに考えるようになる
この結果は、「ひとりごとが思考を助けている」ことを示しています。
つまり、声に出すこと=考えること なのです。
「外言」と「内言」ってなに?
| 種類 | 内容 | 特徴 |
|---|---|---|
| 外言(がいげん) | 声に出して話す言葉 | 子どもが今考えていることを“音”にして整理する段階 |
| 内言(ないげん) | 頭の中で話す言葉 | 声に出さず、思考や行動を自分でコントロールできる段階 |
ヴィゴツキーは「外言(ひとりごと)」が「内言」へ変わることこそ、人の思考の成長だ
と述べました。つまり、外言→ひとりごと→内言 の過程を経て成長していくということです。
ですから、ひとりごとは「静かな思考」への第一歩。
むしろ、「考える力が育っている」と見るべきなのです。
見守る大人ができること
● 1. 否定せず、まず観察
「またひとりごとを言ってる」ではなく、
→「今どんなことを考えてるのかな?」と見守りましょう。
子どもが言葉を使って考えている最中かもしれません。
その瞬間に「静かにして!」と止めてしまうと、思考の流れを断ち切ることになります。
● 2. 優しく共感する
子どもの言葉に耳を傾け、「そうなんだね」「上手に考えてるね」
と一言添えるだけで、“自分の声を大切にしてもらえた”という安心感につながります。
この安心が、自己表現力と社会性の育ち を支えます。
● 3. 遊びに取り入れる
- 絵本の登場人物の「ひとりごと」を想像してみる
- お片づけをしながら「おもちゃさんも『おうちに帰るね〜』って言ってるね」
- ごっこ遊びで「お医者さん、今なに考えてる?」と話を広げる
こうした工夫で、言葉を“楽しむ”時間 が増えます。
子どものひとりごとは――
- 思考を整理する「声に出す思考」
- 感情を整理する「心のリハーサル」
- 社会性を育てる「対話の練習」
ピアジェは「未熟」と見ましたが、
ヴィゴツキーは「発達の証」と捉えました。
現代の教育心理学では、ヴィゴツキーの考えが広く支持されています。
つまり、ひとりごとが多い=よく考えている証拠 なのです。
今日のおさらいQ&A3問
Q1. うちの子、よくひとりでブツブツ言ってるけど大丈夫?
A.まったく問題ありません。それは“考える練習”をしている証拠です。子どもは言葉を使って、自分の気持ちや行動を整理しているんです。むしろ、思考力や社会性が伸びているサインです。
Q2. ひとりごとが多いと「友達と遊べてないのかな?」って心配になります。
A.実はその逆。ひとりごとは、友達との関わりや会話を自分の中で再現している時間なんです。遊びで経験したやり取りを“ひとりごと”として整理しているだけ。社会性の芽がしっかり育っている証です。
Q3. ピアジェとかヴィゴツキーの考えは、なにが違うの?
A.ピアジェは「ひとりごとはまだ未熟」と考え、ヴィゴツキーは「成長の途中で大事なステップ」と考えました。今ではヴィゴツキーの“発達の証”という考え方が主流です。
☆ご希望の方はオンライン15分何でも相談(無料)をご利用ください。
〇 無理な勧誘なし 〇 パパ・ママどちらの参加も歓迎 〇カメラOFFでもOK 〇LINE通話で実施
※お申込みは公式ライン、もしくはお問い合わせフォームから「無料面談希望」と記入してご連絡ください。
☆体験ベビーシッター(2,000円/1時間 ※特別価格(税込)最大4時間)も募集しています。
体験後にすぐご入会いただく必要はありません。
幼児教育は「今しかできない」貴重な教育です。
今しかできない「幼児教育」──リコポ幼児教育が選ばれる理由
ご家庭に合った最適なサポート方法を、ゆっくり一緒に考えていきましょう。
執筆:中山 快(株式会社リコポ 代表)