子どもの未来を変える「メタ認知」とは?幼児期から育む最強の学習力
私が子どもたちに勉強を教えているとき、最も伸びる子はどんな子だったか、と問われるならば、答えは一つです。「自分に何が不足しているか考えられる子」です。
例えば英語の単語を勉強するとき、覚えるにはいろいろな方法があります。書いて覚える、読んで覚える、アプリを使う、単語帳を使う、単語シートを使う、英語の長文から覚える、いろいろな方法がありますが、経験上最もダメな子はそもそも勉強しない子です(当たり前ですが)。なぜか自分には能力があり、100単語も一日50個覚えれば、2日で覚えられると勉強に取り掛からない子は結局やりませんし、伸びません。そんなにあまくない。次にできない子は、意外かもしれませんが、先生の言うことをそのまま聞く子です。先生が「ちゃんと書いて覚えなさい」と言うと、そのままひたすらに書いて覚える子、先生の指示が悪く仕方がないこともありますが、人の意見をそのまま受け入れ、結果がでればよいのですが、結果が出なくても、疑わずそのまま、その方法に従い続ける子、このタイプも伸びづらい傾向になります。では一番伸びる子はどんな子か。それは「自分に一番合ったやり方を自分で見つけられる子」です。
子どもたちは個々に性格も、能力も、不足していることも、目指しているものも違います。今の自分をを見つめなおすことができ、何ができないか、何が必要かを分かる子が強い。英単語の場合、自分はアプリを使ったら、スマホが気になって勉強にならないから単語帳を使う。書いて覚えても頭に入らないから、まずは長文を読んで、分からない単語をピックアップして、単語シートに書いてって、それを電車の中で覚えるなど、自分にとって一番よい勉強のスタイルを気づける子は本当に安心できました。
私はこの自分を見つめなおす行為ができる人を「頭の良い人」と考えます。新しいものもどんどん出てきているのに、何でもかんでもできて、知っている人はいません。「何を知らないのか」いわゆる「無知の知」こそ偉大な知性だと思っています。
この自分がどこまで理解しているか、何を知らないのかを冷静に見つめるという「自分を客観視する力」こそ学習の成果を大きく左右するカギが“メタ認知”という力です(無知の知は哲学的意味合いで、この心理学におけるスキルであるメタ認知とは概念が異なりますが)。
自分の考え方や行動を客観的にとらえ、調整できるこの力は、受験勉強だけでなく、将来の仕事や人間関係にも直結する重要なスキルです。しかも、幼児期から少しずつ育むことができます。本記事では「メタ認知とは何か」「なぜ大切なのか」「どう育てるのか」を、わかりやすく解説します。
メタ認知とは何か
「メタ認知」とは、一言でいうと「自分の考え方や学び方を、自分で理解し、調整する力」のことです。
例えば、「この問題はわかっている」「ここはまだ理解が足りない」と自分で気づき、勉強の仕方を変えられる力です。心理学者フラベルが提唱した概念で、自己理解の一種とされています。
- 認知=「覚える・考える・理解する」力
- メタ認知=「自分の認知をモニターして調整する」力
つまりメタ認知とは、指令を出す天の位置にいる自分がいて、その指令を実行する地上にいるもう一人の自分を見下ろしている感覚ですかね(ごめんなさい、分かりづらいですね)。
メタ認知を具体的に説明すると
ということで、もう少し具体例を見てみましょう。
- テスト勉強の場面
「この単元は理解できていないから、もう一度復習しよう」 - 読書の場面
「この物語の登場人物の気持ちがわからない。もう一度読み直そう」 - 日常生活の場面
「今の説明は相手に伝わらなかったな。次は違う言い方をしよう」
このように、簡単にまとめると「自分の理解度や行動を客観的に振り返り、調整できること」がメタ認知の具体的な姿です。
メタ認知はどう役立つのか
メタ認知が高いと、学習効率も生活の質も大きく変わります。
- 勉強の効率化
無駄な暗記や繰り返しを減らし、必要なところに集中できる。復習の仕方がうまくなります。 - 問題解決力の向上
失敗の原因に気づき、次に改善できる。 - 自己管理力
「今の自分は疲れているから休もう」と判断できる。子どもはやらなくてもできるや、面倒くさいからやらないと - コミュニケーション力
相手の立場を考えながら話せる。共感力にも通じます。
※共感力については以前のブログ記事も参考にしてみてください。
(「共感性」を養う幼児教育 「思いやりのある子ども」は幸福度が高い)
人間は失敗から学び、大きく飛躍できます。メタ認知による今の自分を客観視する能力は、受験や社会生活に適応し、成長していくためには必須の力となります。
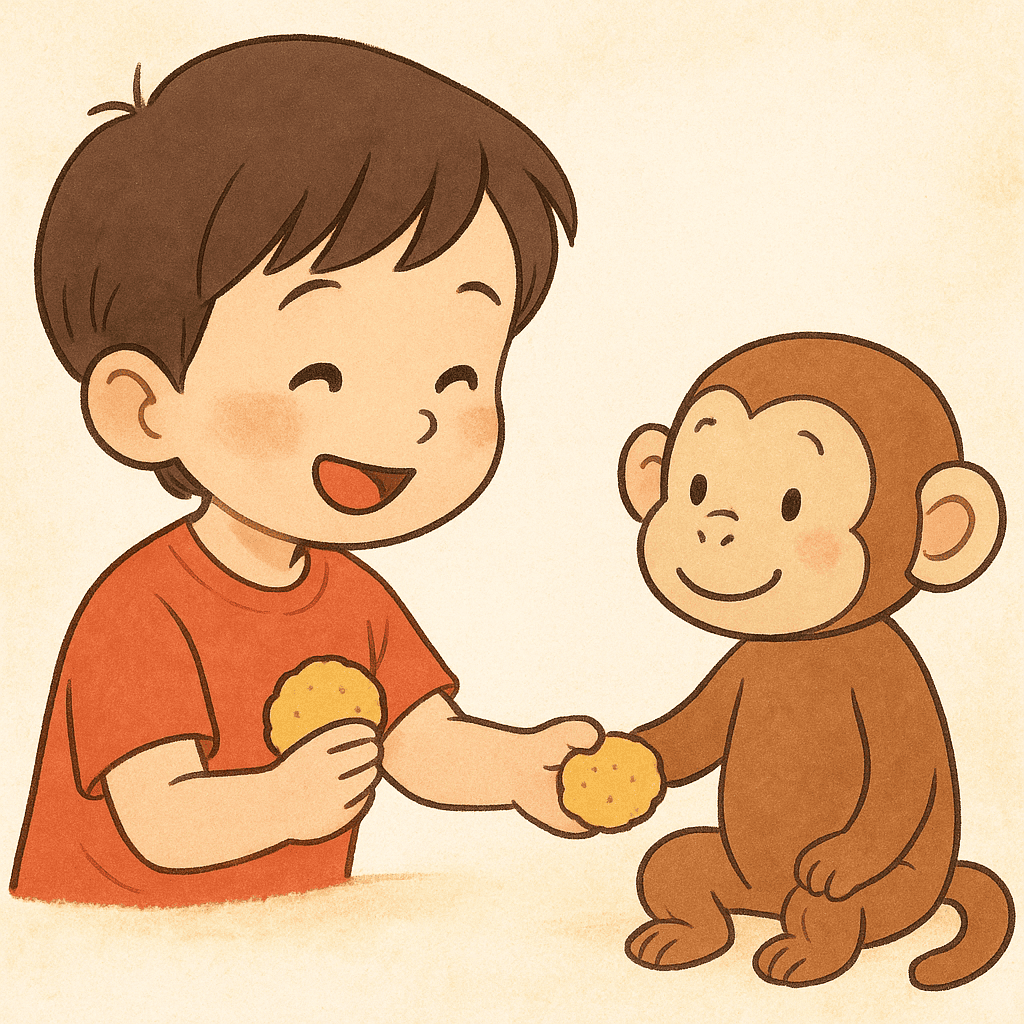
メタ認知は受験勉強や科目学習に役立つ
特に日本では受験勉強が大きなハードルになりますが、メタ認知はここでも大きな力を発揮します。
例えば、
- 数学:「この問題は計算ミスが多いから、解き方の手順を意識しよう」「この問題は苦手な傾向があるから、テストの時必ず見直しをしよう」
- 国語:「要点がつかめていない。作者の意見と、その反論に注目しよう」
- 英語:「単語の暗記だけでなく、文脈で理解しないと身につかないからどんどん長文を読もう」
こうした今の自分の力と向き合いつつ「勉強を見直す」力があるかどうかで、学力の伸びは大きく変わります。
メタ認知は将来にわたって大事な能力
メタ認知は勉強のためだけではありません。大人になってからも役立つ、まさに一生モノのスキルです。
- 仕事で:自分の進め方を振り返り、改善できる
- 人間関係で:相手の気持ちを想像し、自分の伝え方を調整できる
- 人生全般で:感情を客観的に見つめ、冷静に判断できる
「頭の良さ」よりも「自分を客観視できる力」が、社会で信頼される大人をつくります。
メタ認知と幼児教育
ここで気になるのは、「小さな子どもにメタ認知は必要?」という点です。答えはYESですし、この「メタ認知」を成長させるのに非常に重要な時期です。
幼児期は、自分の行動や感情を少しずつ言葉にできる時期です。例えば、
- 「これ難しい」
- 「できた!」
- 「もう一回やりたい」
こうした発言はすでに“メタ認知の芽”です。大人が「難しかったんだね」「できたね!」と共感し、言葉にしてあげることで、子どもは自分の思考や感情を整理できるようになります。
メタ認知はどうやって身につく?訓練の仕方
メタ認知は「意識した」幼児教育により伸ばせます。家庭でもできる方法を紹介します。
1. 子どもに「振り返り」を促す
- 「どうやって考えたの?」
- 「次はどうしたい?」
2. 絵本や遊びの中で気持ちを言葉にする
- 「このキャラクターはどんな気持ちかな?」
- 「君だったらどうする?」
3. 成功・失敗の両方を言語化する
- 「できたね。どうやってできたの?」
- 「うまくいかなかったね。次はどうすればいいかな?」
4. 親自身もモデルになる
- 「ママも最初は間違えちゃった。でもこうやって直したよ」
親が自分の行動を振り返る姿を見せることで、子どもも自然に真似をします。
※幼児期の遊びや生活体験を通じてメタ認知を育む実践例が紹介されています。
特に絵本は登場人物がいて、その行動や目的を語り掛けることはメタ認知にはとても効果があります。
ブログでも記事にしているので、参考にしてみてください。
『しろいうさぎとくろいうさぎ』から考える絵本教育とシッター活用
『スイミー』と幼児教育 〜読み聞かせと会話で育つ非認知能力〜
保護者の方へのメッセージ
子どもに「頑張れ!」と言うだけでは、学びは続きません。大切なのは「どう考え、どう工夫するか」に気づかせてあげること。その土台がメタ認知です。
幼児期に「振り返る習慣」を積み重ねることで、将来、勉強も人生も前向きに切り開いていける力が育ちます。
Q&A(まとめ)
Q1. メタ認知は小さな子どもにも必要ですか?
A1. はい、幼児期から少しずつ育てることができます。例えば「できた!」「難しい」といった発言はすでにメタ認知の芽。親が共感し言葉にしてあげることで、子どもは自分の考えや気持ちを整理できるようになります。
Q2. メタ認知は勉強にどう役立ちますか?
A2. 自分の理解度を把握し、学習法を調整できるため効率的に勉強できます。「ここは苦手だから復習しよう」「この解き方は間違いやすいから注意しよう」といった工夫が自然にできるようになります。
Q3. 家庭でできるメタ認知の育て方はありますか?
A3. 特別な教材は不要です。「どうやって考えたの?」「次はどうしたい?」と声をかけること、絵本や遊びの中で気持ちを言葉にすることが効果的です。親自身が「失敗したけど直せた」と振り返る姿を見せるのも良い方法です。
☆ご希望の方はオンライン15分何でも相談(無料)をご利用ください。
〇 無理な勧誘なし 〇 パパ・ママどちらの参加も歓迎 〇カメラOFFでもOK 〇LINE通話で実施
※お申込みは公式ライン、もしくはお問い合わせフォームから「無料面談希望」と記入してご連絡ください。
☆体験ベビーシッター(2,000円/1時間 ※特別価格(税込)最大4時間)も募集しています。
体験後にすぐご入会いただく必要はありません。
幼児教育は「今しかできない」貴重な教育です。
今しかできない「幼児教育」──リコポ幼児教育が選ばれる理由
ご家庭に合った最適なサポート方法を、ゆっくり一緒に考えていきましょう。
執筆:中山 快(株式会社リコポ 代表)