成長のサインでもある─子どもの“自己制御”を育てる親の関わり方
「うちの子、自己主張が強くて困るんです」
「逆に、まわりに気をつかいすぎて言いたいことが言えないんです」
──そんな相談を受けることが、幼児期には少なくありません。
実はどちらも、子どもの“成長の証”です。
人は、自己主張(自分の気持ちを表す力)と自己抑制(気持ちをコントロールする力)のバランスを通して、「自己制御」という大切な力を身につけていきます。
この記事では、幼児期における自己主張と自己抑制の発達、そして自己制御を育てる関わり方を、世界と日本の文化的視点も交えて解説します。
自己主張と自己抑制──対立ではなく“両輪”
子どもの「自己主張」と「自己抑制」は、対立するものではありませんが、まずはしっかり自己主張と自己抑制を区別しておきましょう。
この2つがバランスよく育つことで、社会的スキルや非認知能力(思いやり・共感・がまんなど)が発達します。
そして「自己制御」とはこの2つを合わせたものになります。
| 観点 | 自己主張(assertiveness) | 自己抑制(self-control) |
|---|---|---|
| 内容 | 自分の気持ち・意見を表す力 | 感情や衝動をコントロールする力 |
| 主な年齢期 | 2〜5歳頃に芽生える | 3〜6歳頃に徐々に強まる |
| キーワード | 自立、表現、意志 | 我慢、思いやり、協調 |
| 発達上の意義 | 自尊心や主体性を育てる | 社会性・道徳性を育てる |
「言える子」と「がまんできる子」。
どちらも大切ですが、どちらか一方に偏ると、人との関係づくりに苦労することもあります。
自己主張とは?──「自分の気持ちを外に出す」力
●自己主張の発達と特徴
幼児期の自己主張は、「いやだ!」「ぼくが先!」という言葉に表れます。
これは単なる“わがまま”ではなく、「自分の意志を認識できるようになった」発達の証です。
2歳ごろから芽生える自己主張は、心理学では「第一次反抗期」とも呼ばれます。
この時期の子どもは、他者と自分を区別し始め、「自分の世界」を確立しようとします。
●親が気をつけたいこと
- 否定せず、気持ちを代弁してあげる:「○○がしたかったんだね」
- 単に叱るよりも、“選択肢”を与える:「先にこれをしてから遊ぼうか?」
- 自己主張は「悪」ではなく、「自己肯定感の芽」であることを意識する
※ベネッセの記事です。参考にどうぞ。
イヤイヤ期がはじまった!成長のひとつ、自己主張を受け止めよう!(ベネッセ)
こちらはいつものブログ記事です。こちらも参考にしてください。
「イヤイヤ期」はなぜ起こるの?―心の発達に欠かせない大切な時期―
自己抑制とは?──「感情を内でコントロールする」力
●自己抑制の発達
3歳ごろになると、脳の前頭前野(感情や行動の制御を司る部分)が発達し始め、少しずつ「待つ」「ゆずる」といった行動が見られるようになります。
この時期から、「がまんする」「順番を待つ」経験が、社会的行動の基礎を築きます。
心理学者ウォルター・ミシェルの「マシュマロ実験」では、がまんできた子ほど将来の学業・社会的成功が高かったことが報告されています。
つまり、自己抑制の力は「学力」や「人間関係」にも深く関わるのです。
※マシュマロ実験はかなり有名な実験ですが、この実験や意義に関してはまた改めてお伝えすることにします。
●自己抑制を育てる環境
- 成功体験を積ませる:「待てたね、えらいね!」
- ルールや日課の一貫性を大切にする
- 感情を言語化するサポートを行う:「悔しかったんだね」
自己制御とは?──思いやりと共感を生む“心の筋力”
自己制御とは、自己主張と自己抑制の両方を統合し、状況に応じて自分の感情や行動を調整できる力です。
これは単なる「がまん」ではなく、**「自分をコントロールしながら、他者と調和する力」**です。
自己制御が育つと──
- 友達とのトラブルが減る
- 感情的にならずに話し合える
- 相手の立場に立って考えられる
この力は、やがて「思いやり」や「共感」といった非認知能力の核になります。
ヴィゴツキーも「社会的関わりの中で自己制御が発達する」と述べています。
- 自己主張=自分を表す力
- 自己抑制=感情を抑える力
- 自己制御=そのバランスをとる力
この3つが発達すると、子どもは「思いやり」「共感」「協調」といった人間関係の土台を築きます。
※共感力と思いやりの記事です。参考にしてください。
「共感性」を養う幼児教育 「思いやりのある子ども」は幸福度が高い
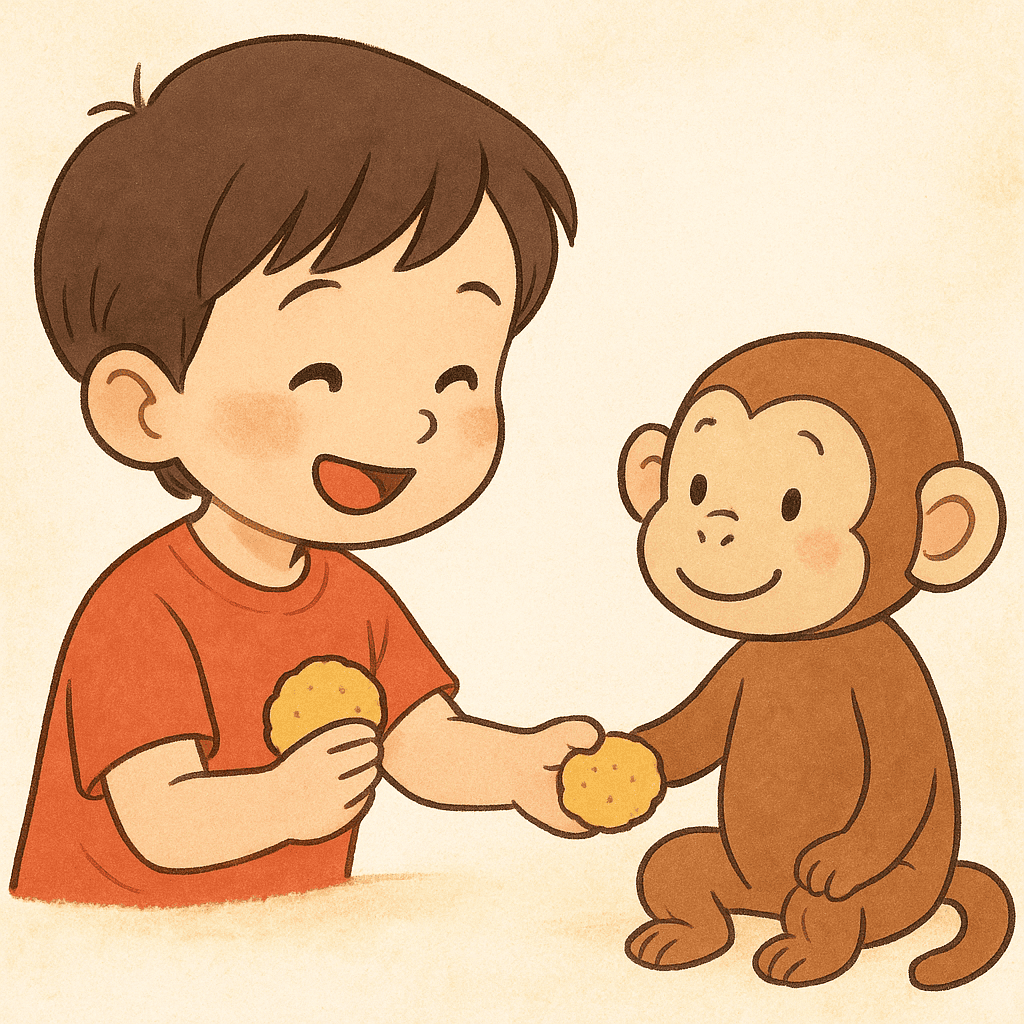
文化による違い──「自己主張」をどう捉えるか
自己主張の意味は、文化によっても異なります。
欧米では「自分の意見をはっきり言う」ことが尊重されますが、日本では「まわりとの調和」がより重んじられます。
| 文化圏 | 重視される価値観 | 教育での傾向 |
|---|---|---|
| 欧米 | 自己表現・独立 | 主張する練習を促す |
| 日本 | 協調・思いやり | 控えめで空気を読む行動を評価 |
どちらが正しいというより、社会や文化の中での「自己制御の形」が違うのです。
日本の子どもたちにとっては、「主張する勇気」と「場を読む力」を両立できる環境が理想です。
自己制御を育てるために──親ができる5つのこと
- 感情に名前をつける:「今、悲しい気持ちなんだね」
→ 言語化が感情コントロールの第一歩になります。 - “待つ”を楽しくする:タイマーを使った「待てゲーム」などで楽しく練習。
- モデルを見せる:親自身が落ち着いた対応を見せることで、模倣学習が起きます。
- 成功体験を認める:「がまんできたね」「話せてえらいね」と具体的に褒める。
- 安心できる関係性をつくる:不安が少ないほど、感情を自分で整理しやすくなります。
「主張」と「抑制」をバランスよく育てることの大切さ
自己主張だけでは衝突が増え、自己抑制だけではストレスが溜まります。
大切なのは、「伝える力」と「聴く力」のバランス。
これが整うと、子どもは人間関係の中で“自分らしさ”を保ちながら他者と調和できます。
親が「主張を尊重しつつ、抑制を促す」姿勢を見せることで、子どもは自然にそのバランスを学びます。
今日のおさらいQ&A3問
Q1. 自己主張が強いのは悪いこと?
A.いいえ。自分の意志を持てる大切な発達段階です。言葉で伝える練習をサポートしましょう。
自己抑制は何歳ごろ育ちますか?
A.3〜6歳頃から徐々に発達します。遊びや生活習慣の中で「待つ」「ゆずる」経験を積ませましょう。
Q3. 自己制御を家庭で育てるコツは?
A.感情を言葉にし、親が落ち着いた行動でお手本を見せることが最も効果的です。
☆ご希望の方はオンライン15分何でも相談(無料)をご利用ください。
〇 無理な勧誘なし 〇 パパ・ママどちらの参加も歓迎 〇カメラOFFでもOK 〇LINE通話で実施
※お申込みは公式ライン、もしくはお問い合わせフォームから「無料面談希望」と記入してご連絡ください。
☆体験ベビーシッター(2,000円/1時間 ※特別価格(税込)最大4時間)も募集しています。
体験後にすぐご入会いただく必要はありません。
幼児教育は「今しかできない」貴重な教育です。
今しかできない「幼児教育」──リコポ幼児教育が選ばれる理由
ご家庭に合った最適なサポート方法を、ゆっくり一緒に考えていきましょう。
執筆:中山 快(株式会社リコポ 代表)